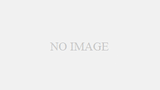今朝、日経電子版でこんな記事を見かけた。
日立製作所は7月にも、事前に職務の内容を明確にし、それに沿う人材を起用する「ジョブ型雇用」を本体の全社員に広げる。管理職だけでなく一般社員も加え、新たに国内2万人が対象となる。必要とするスキルは社外にも公開し、デジタル技術など専門性の高い人材を広く募る。年功色の強い従来制度を脱し、変化への適応力を高める動きが日本の大手企業でも加速する。
2022年、日立製作所が打ち出したジョブ型雇用の全社導入は、日本企業における雇用制度改革の象徴的な一歩でした。管理職のみならず一般社員までを対象にし、職務内容に基づいて人材を起用する制度へと大転換。対象は国内2万人に及び、年功序列から脱却した実力主義へのシフトが本格化します。
社外にスキル要件も公開し、デジタル人材など高度専門職の確保にも積極的。こうした取り組みは、変化の激しいグローバル市場で生き残るための選択に他なりません。
年功序列では優秀な人材を確保できない時代
長年、日本では「ジョブ型雇用は馴染まない」とされてきました。しかし、実力ある30歳のIT人材が年功序列で700万円しかもらえない――そんな企業に誰が魅力を感じるでしょうか?
市場価値が2,000万円あるような人材なら、当然、年功ではなく職能と成果に応じた報酬を求めてきます。
企業が真に競争力を持ち続けるには、報酬制度を含めた構造改革が不可欠。日立はその苦しみを引き受けながらも、確実に変化を遂げつつある企業だと感じます。
東芝も再起を賭けたスピンオフ戦略へ
一方、東芝も大胆な動きを見せています。企業を分割し、それぞれをスピンオフ上場させるという極めて珍しい戦略を採用。グループ全体としての統合経営ではなく、事業ごとのスピードと裁量を最大化する選択です。
原子力に経営資源を集中した判断は結果的には失敗でしたが、その背景にあるチャレンジ精神と意思決定のスピードは、東芝のDNAに組み込まれたものだと私は思います。
三菱電機は変革を怠ったまま、不祥事に沈む
かつて「総合電機御三家」として並び称された日立・東芝・三菱。
その中で、変化に最も消極的で、改革が進んでいないのが三菱電機です。
過去の選択と集中戦略によりリーマンショック後も一定の安定を保っていた三菱ですが、2021年以降、相次ぐ不正品質検査、ブラック企業大賞の受賞、社員の自殺、社長の辞任といった暗いニュースが続きます。
社内風土の旧態依然ぶり、年功序列の温存、経営スピードの鈍化――これではグローバルな舞台で戦えるはずもありません。
株価が示す企業の実力と将来性

リーマンショック以降の株価推移を見ると、日立はV字回復から長期上昇トレンドを描いています。東芝も粉飾決算による低迷を経て、ようやく再評価されつつあります。一方の三菱電機は、安定こそあれ、成長性の面では完全に取り残されつつある印象です。
総合電機の未来:「誰が勝ち残るか」はもう見えている
私はこう考えています。
日立=野武士のような機動力と変革力 東芝=失敗から立ち上がろうとする執念とスピード感 三菱=変化を恐れ、上層部に忖度する“昭和的サラリーマン組織”
この三者の中で、真に生き残るのは誰か?
答えはすでに明らかです。
三菱電機はこのままでは没落の道をたどるでしょう。
まとめ:企業に必要なのは「変化への覚悟」
今、総合電機各社は大きな岐路に立たされています。
過去の栄光や安定にすがっていては、生き残ることはできません。
求められているのは、時代の変化に合わせた抜本的な改革と覚悟です。
それができる企業だけが、これからの日本を背負っていく存在になれると信じています。